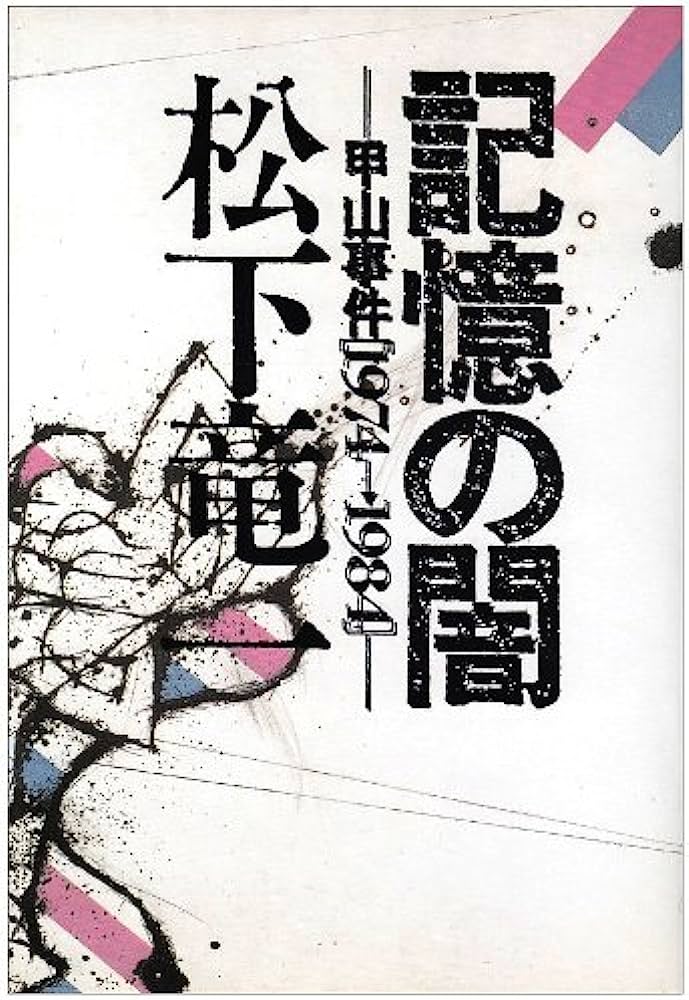
二人の園児の遺体が発見されたマンホールの蓋は重さが17キロある。警察はこの重さでは園児には開閉できないと最初から決めつけ、「大人による犯行」として捜査を始めた。また甲山学園は外部から隔離されており、侵入の形跡が見られないことから、「内部犯行説」、すなわち当時30人在籍していた職員の犯行に捜査が絞り込まれた。
甲山学園は6歳から24歳までの79人の知的障がい者が入所していた。つまり入所者には年長者もいたし、体格の良い者もいた。彼らは日常的にマンホールの蓋を開閉して、中に石やおもちゃを投げ入れて遊んでいた。殺人であれ、事故であれ、最も現場のことを知っていたのは園児だったのだ。「知的障がい者に殺人ができるはずがない」と決めつけた初動捜査の誤りは、次は女性差別へと向かう。
「女性犯人説」
「女性には理性がない」「女性は生理の時には何をするかわからない」という根拠のない偏見にもとづいて、「このような残酷な事件を引き起こすのは女性にちがいない」と女性犯人説に絞り込み、女性職員に生理日を報告させるなどの差別的な捜査を進めていた。
最終的に警察は保育士のSさんを犯人と断定して逮捕した。その理由は「亡くなった園児の葬式で最も取り乱して泣いていたのがSだった」という驚くべきものだった。Sさんは田舎から出て来たばかりの純朴な女性で、警察に対して信頼感を持っていた。素朴な素直さが警察に利用された。日頃世話をしていた園児が無残な姿になったのを目の当たりにして、取り乱してしまうのは当たり前のことであり、それだけSさんが情愛の深い、子どもへの思いが深い保育士だったということだ。それをもって「犯人と断定」した捜査員たちの信じられないような非人間的な感性は、女性差別に深く根差したものだった。
しかし、何の物的証拠もない逮捕であったため、Sさんは一旦は不起訴となり釈放された。Sさんと職員たちは不当な人権侵害が行われたとして、国家賠償請求訴訟を起こした。これに対して警察は、世間の注目を集めていた甲山事件で「面子をつぶされた」とばかりに報復に打ってでた。彼らはありとあらゆる卑劣な手を使って、園児と保護者と職員を分断し、対立・反目させた。その結果、Sさんの不起訴に対して、遺族が検察審査会に不服を申し立てた。
警察は一部の園児を差別的に誘導し利用して「Sさんが死んだ園児を連れ出すのを見た」という証言をさせた。1978年、Sさんは殺人罪で再逮捕され、さらにSさんのアリバイを証言した園長のAさんと保育士のTさんも偽証罪で逮捕された。こうして長期にわたる甲山裁判が始まった。25年後に3人は完全無罪判決を勝ち取ったが、彼らの人生が取り返しがつかないほど踏みにじられた歳月は重い。
「穢れ」「家の恥」
日本では戦前戦後一貫して、障がい者は「穢れ」「家の恥」として、乳幼児の頃に家族に殺されたり、重度障がい者は「座敷牢」という物置に閉じ込められたりして一生を終えた。社会福祉の貧弱さもその原因のひとつだ。
軽度であっても「劣った命」として塩をまかれ、学校からも排除され、教育を受けることもできず、肩身の狭い絶望的な人生を強いられてきた。1960年代後半から、ようやく障がい者の人権が語られはじめ、施設や養護学校が作られていった。しかしそれは、人里離れ、地域から切り離された場所への隔離収容だった。そこでは不妊手術が強制され、トイレや風呂の介助を異性が行うなど、障がい者の人権は蔑ろ(ないがしろ)にされてきた。
前述した1970年横浜市で母親が障がい児を殺害した事件では、比較的「良心的」とされた意見でさえも「施設がもっとあれば母親を追いつめずに済んだ」という母親への同情による減刑嘆願運動だった。そこには障がい者の立場はない。
「人間宣言」
それに対して障がい者たちは親や施設や教師、そして世間そのものとの対決を辞さず、「施設解体」「地域での自立生活を」「健常児と同じ地域の学校へ」と叫び、断固として決起した。不自由な身体で、今まで介護をしてくれていた存在との決別さえも覚悟しての決起、どれだけの勇気が必要だったか!
虐げられた長い歴史に爪を立て、杭を打ち、決別して「人間宣言」を発したのである。
1歳半の時に母親が無理心中を図るところから人生をスタートした「青い芝の会」の古井正代さんは、こう語る。「目を覆いたくなる不幸とは? 生まれることが不幸な人生とは? 誰がそう言うのですか? 私は結婚し三人の子どもを出産し育てあげ、アメリカにも住み、次第に動かなくなる身体も電動車いすを駆使して社会活動にも参加している。老いて身体障がいと認知症になった母親を介護し、私は私の人生を十二分に堪能し、感謝しています」 (おわり)
