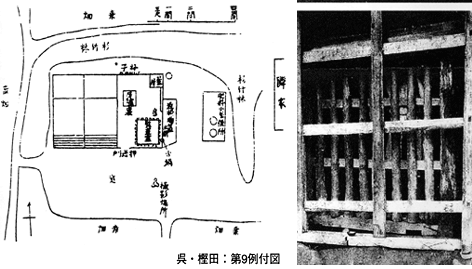
1874年(明治7年)、太政官(だじょうかん)布告として「恤救規則(じゅっきゅうきそく)」が出された。そこでは窮民救済は「人民相互の情誼(じょうぎ)に基づいて行うべき」「国家が安易に貧民救済を行うことは惰民(だみん)の養成につながる」とあり、国民の生存に対する国家の責任を一切認めないというものだった。そのような「国家」こそ不要ではないか。
家畜以下の扱い
戦前の社会事業は宗教家、篤志家、民間の社会事業家によって辛うじて行われていた。1900年には「精神病者監護法」が施行されたが、これも障がい者の医療や福祉とは真逆のものだった。この法律の目的はあくまで「治安の維持」にあり、法律で私宅監置を命じた。私宅監置とは、精神病者を座敷牢(ろう)にいれ、鎖につないで閉じ込めたり、庭の一角に設けられた風が吹き抜けるような掘っ立て小屋に監禁したりするもので、食事やトイレもその場でさせるという、まさに家畜以下の扱いが法律で認められていたのだ。
「日本精神医学の父」と呼ばれた呉秀三(くれ・しゅうぞう、東京帝大教授、注)は、「わが国何十何万の精神病者はこの病を受けたる不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ねるものというべし」と厳しく国の精神病者への処遇を批判した。呉は精神病院の入院患者の手枷(てかせ)・足枷(あしかせ)を禁じるなど療養環境の整備に尽くし、その業績が映画にもなっている。
私宅監置は1950年に精神衛生法が公布されるまで続いた。当時監禁されていた障がい者が、暗い牢の中からこちらを見つめる写真が残されているが、その悲惨さには胸がつぶれる。
さらに語っておきたいのは、沖縄では1972年の「本土復帰」まで私宅監置が続いていたことである。これは沖縄に対する重層的な差別である。私宅監置で使用されていた廃小屋は今も残っている。
国家主義と女性運動
天皇制軍国主義国家はこのような優生思想に基づく差別を構造化していたが、ここで被差別の立場におかれていた女性たちについても述べておきたい。貧窮した民衆が、「娘を売る」ことは昔からあった。売られる先は大抵、遊郭だった。
「文明開化」を掲げていた明治政府は建前上、遊郭を廃止し、「警察が許可した貸座敷業者が、警察が許可した(鑑札を受けた)娼妓(しょうぎ)に部屋を貸す」という公娼制度をつくった。そこでは、娼妓はあくまで「自由意志」で売春を行っていることにされた。まさに欺瞞きわまる国策である。
公娼制度によって江戸時代以上に売春は増加し、性感染症が社会問題となった。娼妓は、「帝国の明日を担う男たちに性感染症をまん延させる元凶」として差別された。そして「男は妻に、妻は胎児に感染させて障がい児や虚弱児を産む」という論理で、「日本民族の質を低める」という優生思想と連鎖していった。
日本基督教婦人矯風会や、平塚らいてうや市川房枝らの新婦人協会の廃娼(はいしょう)運動も、虐げられた女性の立場に立つものでは全くなかった。国家主義に絡め取られていった女性運動は、残念な事に「軍医が管理する安全な性の快楽を兵隊に与える」という戦時中の発想につなげられていったのである。
戦後、優生保護法が超党派の議員立法として成立した(1948年)。戦前と違って、日本国憲法が保障した人権と民主主義の時代を迎えたにもかかわらず、なぜこのような人権侵害の極致というべき法律を許してしまったのか。次号では優生思想の「先進国」と言われる米国の例を見ていきたい。 (想田ひろこ)
(注)呉秀三は1910年から1916年までの間、監置室365カ所、被監置精神病者361人を実態調査した。
