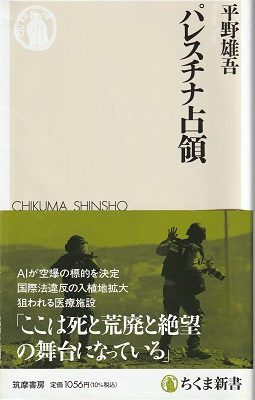
1961年から62年に、エルサレムでのアドルフ・アイヒマン(注)の裁判を傍聴したハンナ・アーレントは、組織の命令に服従するだけの「悪の陳腐さ」と表現し、「全く思考していないこと、それが、彼があの時代の最大の犯罪者になる素因だった」とし、普通の人をして、かくも残虐な大量殺戮を平気で行なわしめる国家の戦争動員やイデオロギーに、注意を喚起した。
建国間もないイスラエルでは、第1次中東戦争が休戦になったばかりで治安も安定せず、社会は「力強さ」を求めていた。「なぜ羊のように従順に殺されたのか」「なぜ抵抗しなかったのか」。ホロコーストはユダヤ人の「弱さの象徴」とされ、侮蔑の対象でもあったという。
ベングリオンらシオニスト指導層は、伝統的ディアスポラ(離散)ユダヤ人を受動的で弱い存在とみなし、力強く生産的な「新しいユダヤ人」を掲げた。かかるなか、イスラエルシオニストは、この裁判を一大イベントとして徹底的に利用したと…。
アウシュビッツ生存者の証言
裁判では、アウシュビッツの生存者を120人も証言台に立たせ、生々しい殺戮の証言や、気を失う証言者の映像は、映像・ラジオ・新聞の報道で、イスラエルの大多数の市民に突き刺さった。「ユダヤ人国家があれば、ホロコーストはなかった」と語られ、イスラエル国家の存在意義が語られてきた。ホロコーストの記憶がイスラエルのユダヤ社会に根づき、「ユダヤ民族の共通の記憶」として「ナショナルアイデンティティへ昇華させた」のは、この裁判においてであるという。
「国家こそ」の教育
「国家がなかったから虐殺された」「ユダヤ人の避難場所としてイスラエルを守る」ことが、教育の場で政治の場で繰り返し訴えられ、「(国民に)国家を守るためには、殺し殺される準備を求めた」というほど、徹底的に教育した。かつての日本か、と思われるほど…。ホロコースト教育の核心は、「新たなホロコーストに準備する必要がある」ことに主眼があり、「恐怖」を基盤にしている。ナショナリズムは国防意識へ導かれ、幼稚園からホロコースト教育が始まり、高校ではアウシュビッツ見学学習があり、直後に徴兵されイスラエル軍に組み込まれていく。
欧州諸国の「罪悪感」
他方、「ホロコーストでユダヤ人に支援の手を差し伸べなかった」欧州諸国、「我々に説教する権利はない」と罪悪感を持ち続ける欧ことが州諸国に突きつけられた。
イスラエルの心理学者は、この「被害者意識」の増殖が、①道徳の崩壊=ユダヤ人は歴史的迫害の被害者で、敵を倒すには道徳的意識に縛られる必要がない、②道徳上の権利獲得=ユダヤ人に脅威を与えるものは誰であれ、危害を加えてもよい、③道徳上の沈黙の強要=「他国はユダヤ人に道徳を垂れるな」などの現象を生んだという。
「平和へ」草の根の動き
教育が、過去の苦しみを盾に現在の暴力を正当化し、他者との関係性を学ぶ機会を奪っていく。アーレントの指摘がブーメランのごとく、イスラエルの人々に、またわれわれにも飛んでくるようだ。どうして、ホロコーストを経験したユダヤの人々が、パレスチナの人々の苦しみを理解できないのか、素朴な疑問が少し溶けた。
しかし、筆者はイスラエルの「ベツェレム(注)やピースナウ」「人権のための医師団」などの人々が占領の不当性を訴え、そうした動きは、10・7以降、草の根レベルで着実に広がっていると付け加えることも忘れない。(啓)
*(注)アイヒマン ナチスドイツの親衛隊将校、数百万人におよぶユダヤ人を強制収容所へ移送した指揮者。/ベツェレム イスラエルの占領下、パレスチナ人に対する人権侵害を記録し、その存在を否定する行為に対して行動する団体)
