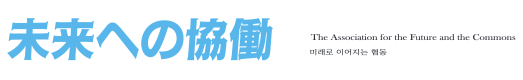ホロコーストの研究者で『歴史修正主義』(中公新書)の著者・武井彩佳さん(学習院女子大教授)の話を聞く機会があった。
武井さんによれば、1945年当時、ユダヤ人にとっての「ドイツ」とは、親兄弟の血に染まった「呪われた土地」であったという。ユダヤ人とドイツ人の間に横たわる「600万人の死者」はいかなる「和解」の試みも挫くかに思われた。
西独がユダヤ人と関係を結び直す原点となったのが、強奪したユダヤ人財産の返還とナチ迫害への金銭補償(10兆円以上と言われる)から生まれた経済関係だった。1952年、ドイツ政府がイスラエルの全般補償請求を認めたルクセンブルク協定によって〈罪の清算〉プラス〈イスラエルとドイツの経済発展〉の構造がつくられる。イスラエル国内では、「血のついた金は死者の尊厳を踏みにじる」と連日反対デモが起こったが、ベン=グリオン(当時イスラエル首相)はその反対を押し切った。
西独からの経済援助によって、イスラエルはパレスチナの実効支配を確立した。西独の補償の4分の1がイスラエルの軍隊に姿を変えた。
アラブ諸国の異議に対して、アデナウアーは、「ドイツに、パレスチナ難民問題に立場を表明する権利はない」(1953年)と発言し、〈補償問題〉と〈パレスチナ問題〉を切り離す方針をとった。
戦後の西独の官僚機構や司法機関はナチ時代からの人的な連続性があった。アデナウアーはあえて彼らの過去を不問にし、社会の中に統合していった。西独にとっての「贖罪」とは、「ユダヤ人国家の存続」のことだった。1968年、西独の学生たちは、ナチスに加担・同調していた親世代に反省を迫るが、「ホロコーストとパレスチナ問題は別次元の問題」とする国是を崩せなかった。イスラエル批判は「反ユダヤ主義」と非難され、「親ユダヤ主義」が国内の規範として確立していく。
武井さんの話を聞いて、ドイツ政府の姿勢が、単なる理論的な問題ではなく、歴史の歪曲に政治と経済の問題が複雑に絡みあっていることが理解できた。一筋縄で解決できるものではない。(啓)