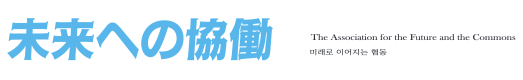子どもの頃、学校給食で脱脂粉乳を飲まされた記憶のある方もいるだろう。「豚のエサ」と揶揄されるほど不味かったが、それでも「敗戦日本を餓死から救うためにアメリカから送られた救援物資だ、ありがたく思え」と言われたものだ。戦後米国は自国の余剰農産物の捌け口として、従属国日本を利用し続けてきた。1960年代は国産の麦や大豆が壊滅的打撃を受けるほど、日本政府は米国の農産物を買い続けた。80年代には牛肉輸入の自由化によって、酪農家を苦しめ、90年代には離農・廃業する酪農家が激増した。一体どこの国の政府なのかと疑ってしまう。米国の顔色を見ることだけが政府の仕事ではないだろう。自国の農業を維持することの責任の方がはるかに重いはずだ。
昨年11月、国は「生乳が余ったから、牛を殺せ」「1頭あたり15万円の補助金を出す」という緊急支援事業を発表した。これで4万頭の削減を目指しているという。一方、ヨーロッパで生乳が生産過剰になったときは、そのまま搾乳を続けて乳製品を作り、それを国が買い取って生活困窮者に無料配布したという。何たる違いだ! 乳牛は一日でも搾乳しなければ乳腺炎を起こして病死する。酪農家の苦悩を政府は分かっているのか!
農産物の輸入自由化を見直し、農家への価格補償や所得補償を実施し、農業に誇りと未来を感じられるようにすることが国の仕事だ。トヨタ車を売るよりもよほど大切なことだ。農業所得に占める政府補助金の割合はドイツ77%、仏64%、ところが日本は30%に過ぎない。日本の国民一人当たりの農業予算は、米・仏の半分、韓国の3分の1である。
日本の農政を抜本的に改革し、食糧自給率の向上を最重要の政策に位置づけること。非正規労働者4割、子どもの貧困(なぜ育ち盛りの子どもが夏休み明けに痩せて登校するのか!)。子どもに満足な食事も与えられない国などいらない。汚染水問題で、海を汚して日本政府は世界の人びとに詫びの一つでも入れたのか。世界は海でつながっている。とりわけ日本近海の韓国、台湾、中国、そしてロシア、北朝鮮の人びとにも頭を下げろ!(想田ひろこ) 〔おわり〕