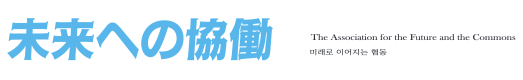「郵政事業はこのままで大丈夫か」
こうした不安が郵政の現場労働者にも重くのしかかっている。昨年12月18日、郵便料金値上げ検討が報道されたことが大きい。24年秋以降、はがきや封書を3割超値上げするという内容だ。
ただでさえ減っている郵便がこれでますます減ることになるだろう。「それでも値上げしないと郵政事業がもたないのではないか」「そこまで厳しい状況にあったのか」と受け止める労働者もいた。この値上げをもってしても「一時しのぎにしかならない」という報道もあった。
こうした中で、「賃上げどころではないのではないか」と思わされる労働者もいたのである。
労働者にしわ寄せ
この郵便料金値上げにかんするパブリック・コメントが昨年12月19日から約1カ月間募集された。そこにJP労組も意見を寄せていた。その内容があまりにも酷い。
まずそのスタンスだが、「経営努力による収益改善やコスト削減等に取り組み、一昨年度までは継続的に郵便事業の収支を黒字としてきた」とまるで会社と同じ。さらに経営努力の具体的中身として「非正規雇用化と、従来の正社員よりも賃金設定の低い新一般職制度を創設することで人件費を抑制してきた」と、自分たちが非正規雇用を拡大させ、正社員の中に低い労働条件の新一般職を作ったことを認めている。
その結果、条件の低い新一般職や若年層から常に改善が求められているため、賃金改善の取り組みは新一般職などを優先せざるを得ず、中高年層の賃上げを棚ざらしにせざるを得なかったかのように言い繕っている。そうして「働く者の負担による事業の維持はすでに限界」だから、「案通りの値上げは当然」とし、「適時適切な価格転嫁を継続的に行える仕組み」にすべきという。すなわち今後はいつでも値上げできるようにすべしと主張しているのである。
JP労組は、労働者全体の賃上げ、労働条件向上に全力で取り組むのではなく、会社と一体的に「経営努力」してきた。しかし、それはもはや限界に来たので、今後は「利用者、国民」負担を強いる政策に率先して協力しようとしている。
続く失策、不祥事
郵政は民営化以降、数々の失策、不祥事を起こしてきた。2010年、JPEXに係る特別損失797億円を計上、翌11年、一時金を削減した。15年にはトール社を6200億円で買収、17年にはトール社に係る特別損失4000億円を計上。19年には、かんぽ不正が発覚し郵政グループの3社長が引責辞任、20年にかんぽ生命が3カ月の業務停止となった。
さらに21年、トール社に係る特別損失674億円を計上し、同社をわずか7億円で売却。一方で楽天と業務提携、約1500億円を出資。23年、楽天の株価下落により850億円の特別損失を計上している。その後、恒常的な人手不足にもかかわらずヤマト社との協業が発表された。現場には過度の負担感が漂う中、協業のスケジュールは当初予定より後ろにずれている。
こうした経営側の不祥事や失策が連続する中で、7年連続ベアゼロや相次ぐ正社員の労働条件切下げが強行されてきた。にもかかわらずJP労組は抵抗らしい抵抗を全くみせてこなかった。JP労組の言う「経営努力」とは、経営責任を問う労働者の声を抑え込み、全ての責任を労働者に転嫁するに等しいことだった。 (浅田洋二)