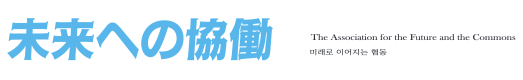早朝、新聞を読んでいたら一挙に暗澹たる気持ちになった。「寿退社」という死語だと思っていた文字が目に飛び込んできたからだ。1985年制定の男女雇用機会均等法に「募集、採用、昇給、教育訓練、福利厚生、妊娠・出産、退職や解雇などについて、労働者を性別を理由にして差別してはならない」とある。もちろんこれはザル法だ。それ故1997年に「努力義務」から「禁止規定」に大幅に改正された。
ところが次に破格の攻撃が待っていた。政府が標的にしたのが「女性保護」だった。1999年、労働基準法の「女性保護」規定が撤廃され、時間外労働の制限や休日・夜間労働の禁止がなくなった。結果、あらゆる職種で女性の残業や深夜労働が拡大した。「権利を偉そうに主張するのなら、女も無制限に働け」というわけである。しかし子育てや家事労働、親の介護などを、ほぼ女性だけに無償労働として強いている現実が一切考慮されていない。
あれから二十数年がたち、非正規雇用の本格的導入により、労働をめぐる現実の社会は男女雇用機会均等法の前提からして失われてしまった気がする。ここでひとまず正規職の女性労働者に焦点をあてたい。
企業は巧みに逃げ口上をこしらえて男女格差をつくる。募集や採用で差別を指摘されて法律に引っかかってはまずいと、男女別である本音を秘して、総合職と一般職に区別する。同じ仕事をしても賃金はじめ全てのルールが総合職に有利であり、そして女性の総合職雇用はエリートを除いてまずない。結局は男女で雲泥の差が生まれる。
4月22日の朝日新聞の記事にある一般職女性は、社宅入居の希望を上司に申請。そこでその上司の返答が、「女性は実家から通い、寿退社する規定になっている」である。確かに社宅入居の資料には「妻帯者向け」となっており、独身であれ既婚者であれ女性はあらかじめ排除されている。この女性はこの企業に山程ある制度的格差に泣き寝入りせず裁判に訴えた。
今年1月の法廷の傍聴席は多くの支援の女性たちが馳せ参じた。かつて自らが原告となって大企業と真っ向から闘い、女性の「道」を作ってきた先輩たちだ。
旧住友化学、商社兼松、野村證券、旧昭和シェル石油などを訴えた女性ら29人は連絡を取り合い、連名の要請書を地裁に提出した。「これまでの男女差別裁判を踏まえ、格差解消の前進に資するものとなるよう強く要請する」。判決は5月13日に迫っている。(当間弓子)